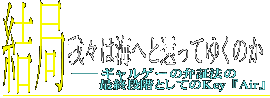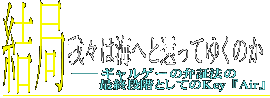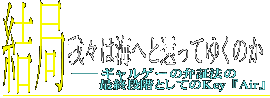
輪廻をモチーフとして人間の意志の問題を極限まで問いつめた文学作品としてよく知られるものに三島由紀夫の『豊穣の海』4部作がある。本多繁邦(だったかな?)という一人の人物を通じて4人の登場人物の輪廻を極めて精緻な筆致で描き扱ったこの作品は、自由意志はあくまで個人に属するものであるのだという近代的人間観の彼方にあり、その帰結として必然的に個人の生命の唯一性・絶対性に疑問符を投げかけている。即ち、個人の生命はその個人のものでありつつも、その因縁においては個人のレベルを遙かに超え、全ての生きとし生けるもの、森羅万象を貫いて存在する根本法則に連なるものであるのだ。この時、私は私でありつつもより始源的な生命としては宇宙そのものでもあり得るのである。このような梵我一如を前提としかつまた理想とする東洋的生命観は、リルケが「私自身の死」と言ったような、またハイデガーが『存在と時間』で示した近代的個人をベースとするあらゆる関係性の根拠を必然的に揺るがす。
言うまでもなく、「恋愛」という行為、関係性は近代の所産である。自己の主観を絶対化するウルトラロマン主義に傾斜したあげく最終的には精神的に破綻した北村透谷が『文学界』などで批判していたように、近代以前には現代のドラマが描くような目的化された恋愛というのは存在していない。『源氏物語』にせよアベラールとエロイーズの往復書簡にせよ、恋愛はあくまでセックスという目的に対する一つの過程でしかなく、そこに絶対の価値は求められていない。それらはいわば文化という形式に還元された前戯に過ぎないのである。確かにこの図式は近代においても保存され、恋愛とセックスの一体化という欺瞞を拡大再生産する事になるのだが、近代における恋愛の一つの特徴はアドルノが渋々ロマン主義についてその功績を認めるように精神的主体としての独立した「個人」がその精神の交わりこそが恋愛の本質であると見倣し、フロムが皮肉るように恋愛を精神的な崇高なものとして絶対目的化することにある。露骨にいえば単なる生殖行為でしかない、あるいは独我的な快感を得るためのものでしかないセックスが三流恋愛小説においてベートーヴェンの交響曲の終楽章の如きクライマックスとして描かれるのはそのような理由に依る。
だがその一方、このような図式はあくまで近代的な人間観に立脚しているものであるのだということを忘れてはならないであろう。もし我々が、人間観もう一つの極、つまり東洋的なそれに軸を移すのであれば、このような恋愛は極めて限定された狭い時空のでの出来事であって、永遠性に眼差しを開いていない狭隘な現象として映ることになるだろう。Keyが作品『Air』を通じて提示した問題の核心の一つは、そこにある。個人を超えた「いのち」に心を向けること。現前の個別者に一喜一憂したり「萌え」たりする意識から、この地球に、この宇宙に遍く広がる森羅万象に心を開くこと。「個人」に限定された日常という時空から、全ての時を貫く人々のいのちのざわめきに意識の全てを解放してそれを見晴らすが為に独り立つこと。そして独り立つことの孤独の彼方にある宥和とは。『Air』のメインシナリオライターである麻枝准氏が同作品で企図したのはその問題系ではなかろうか。
その点から考えれば、『Air』においては恋愛関係とも言うべきものはないに等しかったことは十分納得がいくだろう。『Air』は、Keyのスタッフ達が関わった以前の2作品(『Moon』も入れると3つだが)と比べても圧倒的に恋愛の持つ意味が希薄である。例えば、『One』では過去に耽溺する自我の閉塞としての「えいえんの世界」から主人公が戻ってくることはヒロインとの間に恋愛関係があることを条件としていた。相互が特定の、代替不可能な唯一として相手を求め合うことに奇跡の基盤を求めていたのである。そして、『Kanon』においては恋愛色はかなり薄まるものの(しかしこの場合の展開には麻枝氏の父権主義的な家庭観が多少見て取れるのでそれには賛同する気になれない)、いわゆる「萌え」の要素は商業的な理由もあり残されていた。だが、『Air』の場合、登場する3人のヒロインとの間には観鈴のケースを除けば恋愛感情はまったくみられない。佳乃シナリオは確かに特定の個人に対して自己の能力を犠牲にすることにより成立する幸福というエンディングだが、佳乃の極めて幼い人物造形を考えれば、それが彼女への恋愛感情に由来しているとは到底言えないだろう。また、美凪シナリオでは精神を病んだ母により人格的な危機に陥る美凪自身が自己をみちるを支点とした疑似家庭の中で「母」のロールプレイを行うことで自己同一性を回復しその結果主人公とまた別々の日常を歩いてゆくという展開からして、またいくつかの場面で美凪が甘えることを主人公がきっぱりと拒絶することからしても、「ずっと一緒」的ないわゆる恋愛の物語からは距離を置いていることははっきりと見て取れるはずである。
そして唯一恋愛らしきものが見られる観鈴のDreamシナリオにおいてさえ、その契機となるのは観鈴が持つ人格の独自性ではなく、主人公が抱いていた謎と彼女が苦しむ夢の内容が一致しているということでしかない。相互の間に成立する感情はあくまで保護−被保護に由来するものでしかなく、この点からいえば我々が後輩なり下級生、あるいは子供の面倒を見てやるのとさして変わらない。従って、『Air』においては、我々が日常欲望するような「恋愛」というものは存在していないのだ。
そのかわり、『Air』は先に示したような世界への視座を、視座への契機をもたらそうとしている。個別の存在者を契機とし、なおかつそこに「恋愛」の神話を利用しつつ、「恋愛ならざるもの」、「全ての生命」へと意識を展開させようとさせることは、ドラマトゥルギーの上で多分に力学的な無理を生じさせる。『豊穣の海』の場合は語り部である本多が老いていくということで、また彼自身は色恋沙汰とは縁遠い人間であるという設定(第三巻「暁の寺」ではそれなりに色々あるが)によりそれを巧みに回避しているのだが、語り部=主人公である『Air』は主人公が物語の世界で枢要な役割を演じ続ける限りいずれ破綻を来すことになる。なぜなら、主人公の内面世界の語りはあくまで個別的意識としての主観の表象でなければならず、そうでないとしたら個別の存在者に対する意識も、より限定すれば保護意識も恋愛感情も呈示することができなくなりそれは登場人物という人間によって構成される物語ではなく、思想書の文になってしまうからである。だからこそ最後のAir編ではプレイヤーの視点がそれまでの主人公ではなく一介のカラスである「そら」に変更されるのである。これにより、物語の展開は主人公の意識という〈狭隘なものとしての直接性〉を離れ、登場人物の帰趨という時空におけるそれらの生命の展開へと移ることになるのである。
そうして可能になった新たな舞台装置はゲームとしてはタブーであることを次々に行うことにより「個人」に附与されていた絶対性、唯一性、主観の世界性を粉砕してゆく。上に述べたように通常プレイヤー=主人公であるゲームにおいては主人公の死はゲームの終わりを意味する。それは当然のことである。だが、Air編においてはほぼ明示的に主人公が観鈴の成就を願って消滅する場面が描かれている。この時、主人公は自らが連なっている1000年の「いのち」、そしてそのテロス(古代ギリシャ語で「目的」「終わり」「死」などの意味)を認識している。主人公は自らのが連なるいのちのために、1000年という「途方もなさ」の為に、自らの命の祝福を観鈴に託して消滅するのである。そして、ヒロインの観鈴も、Air編の終盤で幸福な記憶を抱くことによって祝福された死を迎え取る。これは神奈、裏葉、柳也、主人公等と託されてきた「いのち」が観鈴の選び取りにより悲しみの呪縛から解放され、新たな「いのち」として革新された始まりを告げる事を意味する。だから、時空を超えたそうした生命の営みは個々の存在者がその生の中で自らの意志的な行為を行っていくこと、そしてその眼差しを自らにつながる全ての記憶へと向けていることを要求するのだ。この意味からすれば、Summer編でその存在が明かされた「翼人」とは個別的な「今」のみを生きる個人の時間の地平ではなく、永劫の昔からあるいは未来までを貫いて流れるいのちの営みの総体のメタファーであり、そうであるがゆえに「翼人」に由来する者は「今」という地平でしか生きられない個人と関わることは許されていないのだ。それこそがあるいはバイロンが「知恵の実」に見て取ったような「観る者」「知る者」の呪いなのである。時を超えて生きる者は「今」を奪われ、「この」時に生きる者はこの地上から飛び立つことも出来ずただ眼前の直接性の呪縛を現実として生きるに過ぎない。そして、恐らく麻枝氏がギャルゲーに耽溺する存在として暗に批判しているのは後者であろう。
では、「翼人」はいかにしてその必然的な悲しみから自らを終えることができるのか。それは、「翼人」として生きること、即ち超時間的な存在であることといわゆる「個人」として生きることの二項対立を止揚することによってのみはじめて可能になるのだ、ということができよう。先にも述べたように、翼人の生は個々の存在者においてはその主体的な行為を同時に要求する。この対立のゆえに観鈴も夭折する事になるのだが、しかし観鈴がそれに先行するものと異なるのは、彼女がそのような対立を晴子という個別者に徹底的に関わること、武満徹が『Family Tree』のライナーノーツで語っていたように、就中構成された家族という形態に内在的に関わる関係、しかもそれは血縁による必然ではなく、晴子の、そして観鈴の意志によって人為として構成された「疑似」家族(この問題系は『Kanon』と連なり、ひいては麻枝氏の家族に対する考え方に連なる)という人間の日常の営みに観鈴が敢えて関わろうとすることによって揚棄し得たことなのである。
無論、それでも彼女は物語の中で死ぬことになる。だがそれはテロスとしての死なのであり、「翼人」の末裔として彼女が幸福な記憶を以てその全生命を祝福している以上それは個別の事態としては悲劇でありつつも「翼人」の解消あるいは止揚という点においては宥和された始まりであるのだ。
『Air』が極めて難解な作品であると言われるのも、このあたりに理由がある。即ち、「宥和された意識」はそれ自体としては否定的な形でしか示すことのできないものであるからだ。宥和された意識はユートピア(ou-topos,古代ギリシャ語で「(どこにも)ない場所」の意味)性を帯びており、それゆえその在処や姿を明示的に語ることができない。むしろその意識は語ることの隙間からこぼれ落ちるものであり、常に語り得ないものの彼方へと遠ざかる。過剰なまでに雄弁な『Air』のシナリオにおいてもそれは当然然りであり、いかな便法を駆使したところでそれは語り手からは呈示することができないのだ。これに挑戦した麻枝氏の試みは称賛に値すると同時に無謀なものであるとの謗りを逃れ得ないが、むしろ、それは物語における語りえなさを解釈するという点においてはプレイヤーの、日常という現場で普通捉えられることのない超時間的な生命、そしてそれと個別者としての自己の宥和である「どこにもない場所」を重層的に意識しなくてはならない我々の感受性にその核心の展開は委ねられざるを得ないのだ。
だから、この宥和された意識は、物語の上では「そら」の飛翔という形で昇華されているとしても現実には個別者と「翼人」の意識との間で激突する(恐らく)我々の意識にこう告げる。「彼らには、過酷な日々を」と。宥和された意識はそのゆえに「さようなら」という言葉でその希望の在処を我々に暗示するのであり、最後の場面で現れる二人の子供はこの宥和された意識の象徴である。彼らはフーコーが『言葉と物』の最後で予言したように、波打ち際に立つ。彼らは「人間」の終わりであり、「日差しの中 新しい歌、口ずさんでる」(Farewell Song)のである。
我々には、過酷な日々を。眼差しを高くあげて、空へ。